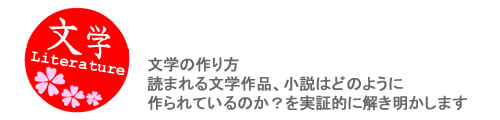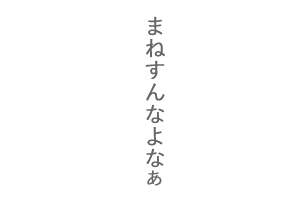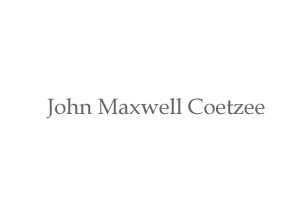安部公房風小説は、こうして作る。その3、安部公房風小説の作り方を体系化してみた。
かまし を意識した「書き出し」で始め、「結び」まで
よどみなく つなげて書かかれた小説
が安部公房風小説のモットーで、謎を要所におき
結末を構成的に工夫して、それによって「次に何が起こるのだろう? 」を考えさせ、
読者の想像力をかきたて、読者に推理させ、読者を物語にまきこむ。
と、読者は能動的にその小説に入り込む。
だが、それは共感ということとは違う。
読者には簡単に想像できないような謎を用意し、
普通に驚くべきことをたんたんと描く、主人公が小説の中で推理するのが安部公房風小説の原則となる。
安部公房の小説を読めばわかるが、
章の途中でもいくつもの伏線が張られ、
読者に「この次にどうなるのか?」を考えさせ、
主人公自身もそれを考えている。
前回書いた
【最終章 結び】の文章の2例目をもう一度見てみよう。
【最終章 結び】
やっと、たどりついた自宅で鍵をかけ身を隠す。
自分の心臓の鼓動だけが聞こえるほどの静寂な時間がながれていった。しばらく寝ていたらしい、ドアの前の壁にもたれて。
何かで急に起こされた。どうやら
アパートの室外の廊下を誰かが歩く音だと気づくのに時間はかからなかった。
灯りもつけずに暗い室内でその音を聞いている。
心臓の鼓動が早まっている。やがて、私の部屋の前で足音が止まる。
(私がかってに書いた小説の終わりの文章です)
この終わり方は、読者の想像力をかきたてる。
結び なのに、「次に何が起こるのだろう? 」と。
ところが、このような小説の終わり方は
動き で始まり、動きで終わるから
みごとな完成形となるといえる。
たとえば、ロシア文学のようにえんえんと情景描写が続いた
書き出しでは、このパターンの終わりでは「書き出し」からの関係性が薄れる。
また、起伏の少ない物語を描いた小説を題材にすると
〝安部公房風〟デフォルメはできない。
小説・文学の模倣は料理みたいなものだ。
そんなわけで、
などでは〝安部公房風〟デフォルメはできないのだ。