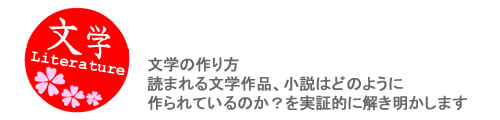小説の会話は、ありえない会話でも許される が・・・
小説の会話はありえない会話でも許される。
98回芥川賞を受賞した池澤夏樹氏の「スティル・ライフ」
の最初のほうの会話を引用するのでみてみましょう。
「何を見ている?」とぼくは聞いた。
「ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って」
「何?
「チェレンコフ光。宇宙から降ってくる・・・」
池澤夏樹氏の「スティル・ライフ」より引用
この会話が現実世界で話されていたら
きざでありえないと思うでしょう。
ところが、このての文章は小説世界では許されてしまいます。
二人のやりとりの部分ではないが、かっこ書きで書かれた
会話を例にとってみましょう。
村上春樹氏の「海辺のカフカ」の最初のほうから引用です。
「君はこれから世界でいちばんタフな15歳の少年になる」とカラスと呼ばれる少年は、
眠ろうとしている僕の耳もとで静かに繰りかえす。
村上春樹氏の「海辺のカフカ」より引用
現実世界では、このような言葉を口に出して言わないでしょう。
こんなふうに、
小説の会話はありえない会話でも許されるのです。
ところが、
このての現実世界ではありえない会話文を
書いてはいけない小説というものも存在します。
それは、何か?
おわかりいただけるでしょうか?
答えはドキュメンタリーの小説と
私小説と、私小説に近い小説なのです。
吉本ばななさんの「哀しい予感」を例にするとわかると思います。
「お腹減った? 何かとろうか?」
「ううん、内緒できたから、もう帰らなくちゃいけないの。」
と私は言った。
「そうね」」
おばはうなずいた。
吉本ばななさんの「哀しい予感」より引用
わかるでしょうか、これは
現実世界でふつうに話されているような会話だなと。
同じ小説でも、ましてや同じ純文学といわれている
ジャンルでもかくも違うものなのです。
書くルールなどない、と言われる小説世界においても
おのずとルールらしいものはできているのです。